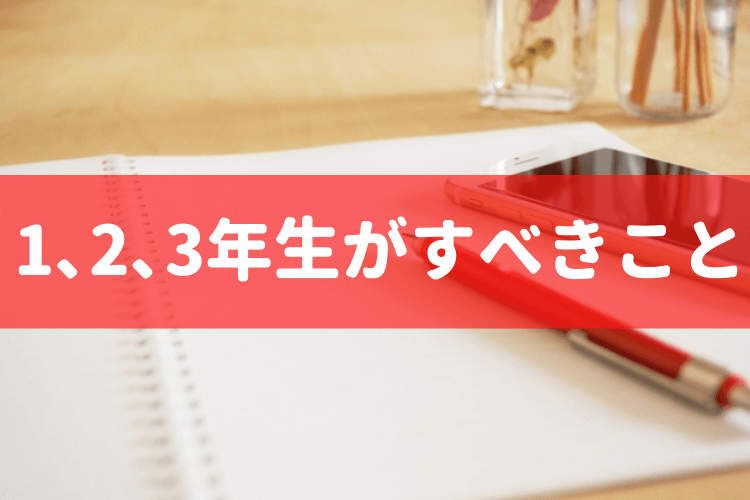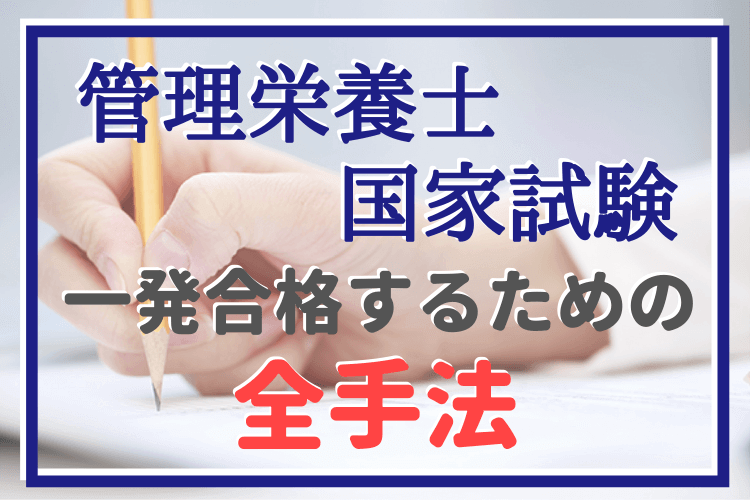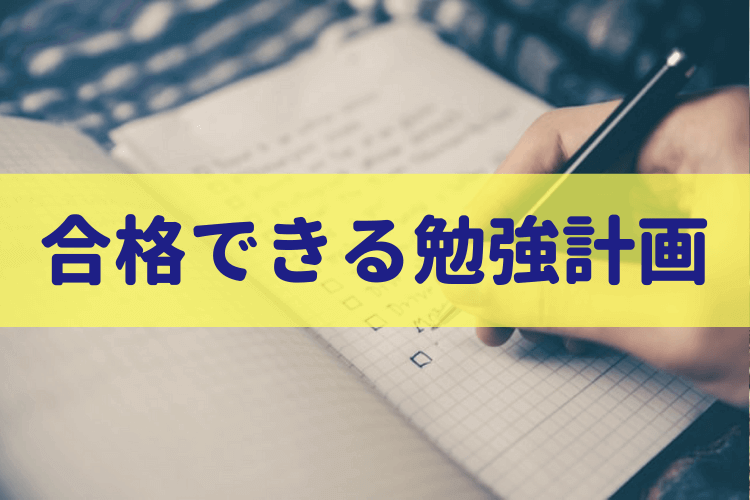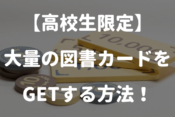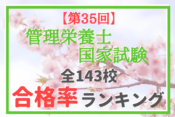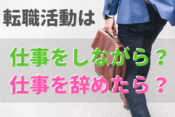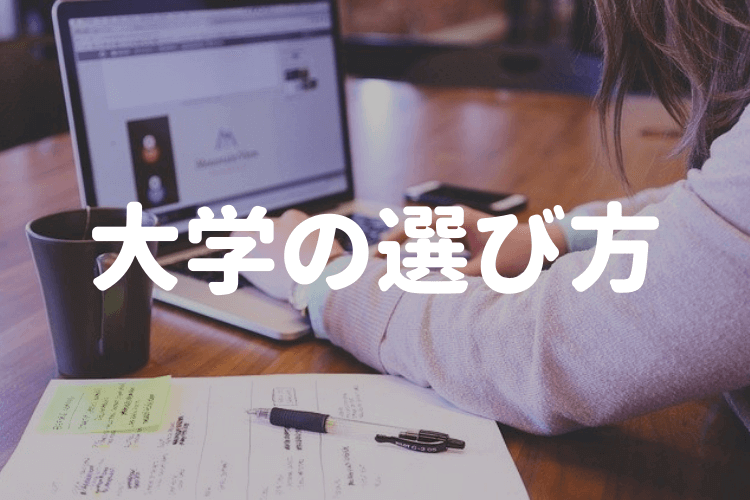【管理栄養士国試対策】模試を受ける目的、上手な受け方、復習方法を徹底解説!

こんにちは!
管理栄養士のサルーです♪
この記事は〝管理栄養士 国家試験の勉強方法〟という記事の一部となっています。
まだ読んでいないという方は、先にこちらの記事をぜひご覧ください!
今回は、模試の受け方や復習方法などについて解説したいと思います!
具体的な内容はこちら!
- 模試を受ける目的
- 模試の上手な受け方
- 模試を使った復習方法
『模試を受けてそのままにしている。』
『模試の復習方法がよくわからない。』
このような人が意外と多いかもしれません!
そこで、あらゆる角度から〝模試〟についてできるだけ丁寧に説明していきます♪
それでは早速みていきましょう!
模試を受ける3つの目的
まずは模試を受ける目的について解説します。
『何のために模試を受けるか?』ということを理解してく必要があります!
模試を受ける目的は次のとおりです!
- 今の実力を正確に知るため
- 間違った問題の知識をつけるため
- 本番に近い状況を体験するため
それでは、一つ一つ詳しくみていきましょう!
①今の実力を知ろう!

これに関しては、ここで解説しなくても、誰もが意識していることではないでしょうか。
模試を受けることによって、現時点でのおおよその実力がわかります。
また、後日しっかりとしたデータとして結果が返ってくれば、全国で自分はどの位置にいるのか?
全体的な問題の難易度がどのくらいだったのか?
このように細かく分析することも可能です。
ここで注意しなければいけないのは、自分の点数を見て一喜一憂しないことです!
気持ちはよくわかります。
しかし、模試を受ける目的はあくまで『今の実力を知ること』ですので、しっかりと自己分析しましょう!
- どの教科の得点率が高い・低いのか
- 解けた・解けなかった問題はどこか
- 自分の知識で解けたか・たまたまか
ザッとこんな感じです。
客観的に答案用紙と向き合うことで、模試を受けるたびに実力がつくこと間違いなしです!
②関連知識を身につけよう!

二つ目の目的は、復習するためです。
模試が終わって、どのような問題が解けてどのような問題が解けなかったのかを把握できたら、次はその問題について知識を深めていきます!
- 実力で正解した → 復習する必要なし
- まぐれで正解した → 復習する必要あり
- 間違った → 理由も含めて復習する
このように、完璧に正答に導けた問題以外は、基本的に復習するのがオススメです!
こうすることで、より一層の知識を深めながら実践に慣れていくことが可能になります。
③本番に近い状況を体験しよう!
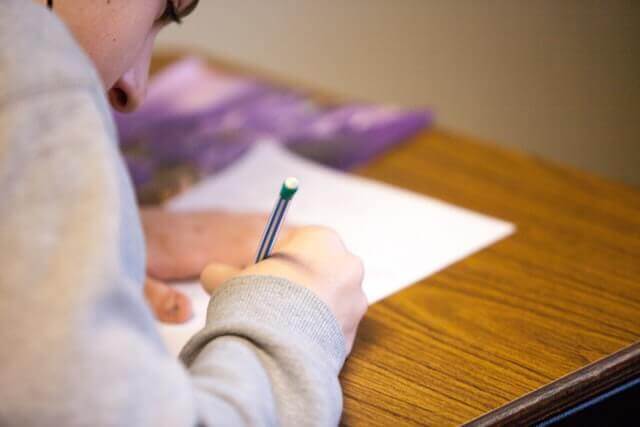
模試を受ける三つ目の目的は、本番に近い状況を体験するためになります。
いくら140点くらい取れる知識量があっても、それを本番で発揮できなければ意味がありません。
現在の自分の実力通りに知識をアウトプットする練習として模試は最適です!
具体的に、模試を受ける際に意識してほしいことは次の5つになります。
- 解答後、見直しをする余裕があったか
- 難問に出会った時にどう対処をしたか
- マークミス回避にどんな工夫が必要か
- 試験前日〜の過ごし方は適切だったか
- 試験間休憩の過ごし方は適切だったか
本番と同じ時刻に模試が始まる場合、本番さながらの準備をして臨むべきです!
前日の寝る時間や休憩時間の過ごし方まで、本番を意識して受けることをオススメします!
復習しやすいように受ける

では次に模試の上手な受け方についてです!
模試が始まれば、問題を解き、マークする。
この一連の作業を200回繰り返していくわけですが、この時にある一工夫をするだけで模試が復習しやすい勉強媒体に早変わりします!
では具体的に解説していきます!
例えば、模試で次のような問題が出たとします!
(せっかくなので、ぜひ解いてみてください♪)
25、血圧調節に関して正しいのはどれか
- 抹消血管抵抗の減少により、血圧は上昇する。
- アンギオテンシノーゲンは、主として肝臓で産生される。
- 副交感神経刺激により、アドレナリンの血中濃度は増加する。
- アンギオテンシン変換酵素により、アンギオテンシンⅠからアンギオテンシンⅡが生成される。
- アンギオテンシンⅡは、アルドステロンの分泌を抑制する。
解けましたか? ちなみに正解は④になります。
この時に、模試の問題用紙そのものに何も記入しないで解いていくのは非常にもったいない!
模試が終わったらすぐに復習できるよう、試験中に次のように問題用紙に書き込んでいきます。
25、血圧調節に関する記述である。正しいのはどれか。
- 抹消血管抵抗の減少により、血圧は上昇低下する。
- アンギオテンシノーゲンは、主として肺肝臓で産生される。
- 副交感神経刺激により、アドレナリンの血中濃度は増加する。
- アンギオテンシン変換酵素により、アンギオテンシンⅠからアンギオテンシンⅡが生成される。
- アンギオテンシンⅡは、アルドステロンの分泌を抑制促進する。
この の部分は、実際には鉛筆で二重線かなんかで消してほしいポイントを表しています。
一方、赤字の部分のように、問題文の横に自分が思う正しい答えを記入していきます!
こうすることで、模試を復習に使う際にどこをどのように間違ったのかが一目瞭然になります。
家に帰ってから、また一から問題を一つ一つ時間をかけて解いたり、自分がわかった問題とわからなかった問題を仕分けする必要がなくなります。
もう一つ、試験中にしてほしいことがあります。
それは、各問題で自分がわかる箇所に解いた感触がわかるように◯、△、×のどれかを記入してください!
それぞれの記号の意味は以下のようになります!
- ◯ → 完璧に解けたと思う問題
- △ → 解くのに少し迷った問題
- × → 全く歯が立たなかった問題
これらを元に自己採点をしていきます。
そして自己採点をしながら、復習する問題か否かの分類をしていきましょう!
では、どのように分類するのでしょうか?
※スマホを横にすると表が見やすくなるよ♪
| 感触 | 結果 | 復習すべきか否か |
| ◯ | 正解 | 完璧に解けて正解→復習する必要なし |
| 不正解 | 完璧に解けたと思ったが不正解→復習 | |
| △ | 正解 | 正解したが、迷った→復習 |
| 不正解 | 迷って不正解だった→復習 | |
| × | 正解 | まぐれで正解→復習 |
| 不正解 | 全くわからなかった→復習 |
このように、◯の記号を書いて正解した問題以外は、基本的には復習する必要があります!
しかし、たまに過去問でも一度も見たことがないような、マニアックな問題も出ます。
その場合は、復習する必要なし!
なぜなら、次の模試や本番でもそのような問題がまた現れる確率は、ほぼ0%だからです。
そういった問題は飛ばして復習しましょう!
このように、自分がどの程度のレベルで問題を解けたのかを記号でわかりやすく記入しておくことで、復習スピードが10倍以上になります!
また、以下の表の赤い部分を徹底的に復習することで、テストの点数が伸びやすくなります!
| 解いた感触 | 正解・不正解 | 復習すべきか否か |
| ◯ | 正解 | 完璧に解けて正解→復習する必要なし |
| 不正解 | 完璧に解けたと思ったが不正解→復習 | |
| △ | 正解 | 正解したが、迷った→復習 |
| 不正解 | 迷って不正解だった→復習 | |
| × | 正解 | まぐれで正解→復習 |
| 不正解 | 全くわからなかった→復習 |
- ◯で不正解 → 勘違いしていた部分が訂正できたら得点に
- △で正解 → 迷った選択肢に関する知識があれば得点に
- △で不正解 → 迷った選択肢に関する知識があれば得点に
このように、◯で間違った問題、△を記入した問題は、復習さえすれば今後は着実に点数を稼げそうな問題ということです。
ですので、ここを徹底的に復習することでテストの点数の底上げが可能になるわけです!
絶対に模試を無駄にせず、上手に活用しレベルアップをはかりましょう♪
模試を使った復習の仕方

模試の復習は、あなたに合った方法でOK!
- 模試専用のノートを作る
- 模試の問題用紙に直接書き込む
- 参考書に模試の問題を切って貼る
このように、復習しやすい方法で大丈夫です。
模試の復習をする目的は『間違ったところをしっかりと知識として習得すること』ですので、どんなやり方でもかまいません!
ただ、ここで一つだけ注意点があります!
学校によっては、『模試の復習ノート』の提出が義務化されているところも・・・
(厳しい学校だぁ〜)
こういった場合に
『とりあえず学校に提出しないと!』
など、目的が『提出すること』にすり替わってしまうような復習ノートは避けてください!
あくまで模試を受ける目的は『あなたのレベルアップのため』です。
ノートを作ると誰もが〝やった気〟になります。
常に目的がブレないように注意しましょう!
まとめ
最後に、今回の記事の内容をまとめていきます!
- 模試を受ける目的は3つ
- 目的① 今の実力を正確に知る
- 目的② 間違った問題の知識をつける
- 目的③ 本番に近い状況を体験する
- 受験時、問題文をできるだけ正文に直す
- ◯,△,× の記号を使いながら問題を解く
- ◯,△,× の記号を元にして復習していく
以上です!