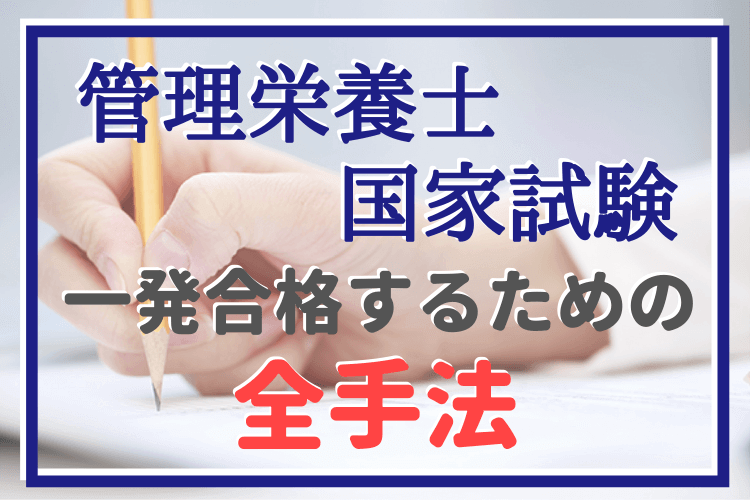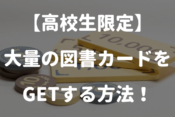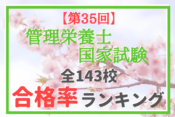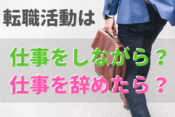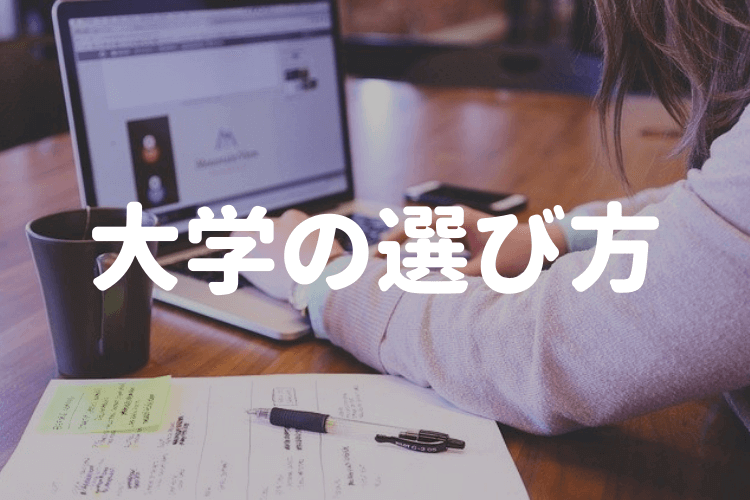【管理栄養士国家試験対策】勉強効率を10倍にすべく〝脳の特徴〟を知っておこう!
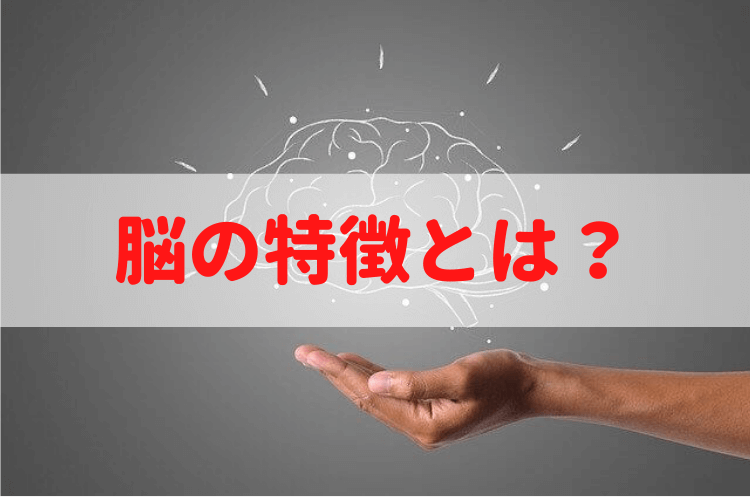
こんにちは!
管理栄養士のサルーです♪
この記事は〝管理栄養士 国家試験の勉強方法〟という記事の一部となっています。
まだ読んでいないという方は、先にこちらの記事をぜひご覧ください!
今回は、私たち人間の脳の特徴について解説していきます!
具体的な内容はこちら!
- 覚えておきたい8つの脳の特徴
- 脳の特徴を生かした勉強方法
我々人間の〝脳〟は、どのような特徴をもち、それを国試対策にどのように活かせば良いのか?
できるだけ丁寧に説明していきます!
それでは早速みていきましょう!
目次
特徴① 脳は鍛えるほど強化される

世界で最も『タクシー運転手泣かせの街』と言われる場所がどこだかわかりますか?
答えはロンドン市内です。
そんな街で、一番〝道〟を覚えている人は誰なのでしょうか?
もちろん、タクシーの運転手さん。
では若い運転手さんと、年配のベテラン運転手さん、どちらが街中の道に詳しいと思いますか?
答えは、ベテランの運転手の方です。
人間の肉体は、年齢を重ねると共に衰えていきますが、脳は唯一と言っていいくらい年齢を重ねるほど強化されていく器官です!
もし筋肉の発達などと同様に、脳も年齢が若い方が能力が高いのであれば、若手のタクシーの運転手の方がたくさん道を覚えているはずですよね?
つまり、記憶というのは訓練するほど強固なものになっていくということです。
では、この脳の特徴を管理栄養士の国家試験対策に当てはめるとどうなるのでしょうか?
何度も何度も国試の問題を繰り返し解くことで、問題を解くための知識を少しずつ記憶することができるようになります。
国試対策は〝繰り返し〟が命です!
特徴② 脳はそもそも忘れる器官である

私たち人間の脳は、そもそも覚えるよりも忘れることに重要性を見出しています。
これは、重要なのでもう一度繰り返しますね!
私たち人間の脳は、覚えるよりも忘れることに重要性を見出している。
『はっ? そんなバカな!』
そう思った人もいるかもしれません。
では実際にやってみましょう!
こちらの9桁の数字を覚えてください。
1、5、7、2、7、8、5、6、4
ではもう一度、今度は目をつぶってこの数字を見ずに繰り返してみください!
おそらくほとんどの人が、ギリギリ覚えられるかどうかだと思います。
もし、9桁の数字が全て言えたとしても、1時間後にやったらほぼ忘れているでしょう。
ではなぜ私たちはこんなにもすぐに忘れてしまうのでしょうか?
それは、本当に大切な情報だけ脳にインプットしておくためです。
先ほどの9桁の数字のように、特に意味のない情報はさっとすぐに記憶から消えるようなシステムになっています。
一方で、友達や彼氏・彼女、夫・妻、親・子どもなど、大切な人との約束はどうでしょうか?
『明日、17時に渋谷のハチ公前ね!』
と約束すれば、間違いなくあなたは翌日の17時にハチ公前に立っているでしょう。
この約束事は、あなたにとって『意味のある大切なこと』ですので、数日くらいは覚えておくことができます。
このように、脳というのは生きていく上で重要な情報から優先的に記憶する特徴があります。
では、管理栄養士の国家試験対策のための参考書に書いてある情報はどうでしょうか?
勉強を始めて間もない人にとっては、まだ特に意味のある情報ではありません。
ですので、面白いくらい一瞬で忘れます!笑
では、どのようにして意味のある情報と脳に認識させ、記憶として定着させるのか?
それは簡単です。
繰り返しその情報に触れることです。
そうすると、脳は次のように判断します。
『あれ?この情報は前にも一度入ってきたぞ!大切かもしれないからとりあえず記憶の中へしまっておこう。』
これが適度な期間をあけて、複数回繰り返されると次のように判断されます。
『お!この情報は繰り返し何度も入ってきているから重要な情報のはずだ!』
こうなると、脳は忘れないように記憶して情報をいつでも取り出せるようにするのです。
つまり、脳は忘れることを前提に勉強し、脳が忘れないように何度も情報に触れる努力をすれば、記憶の定着率が上がります。
特徴③ 脳は細かい情報が苦手

脳は、最初は情報を大雑把にしか受け入れることができません。
例えば、フルクトース(果糖)について勉強するとしましょう!
その時、いきなり『フルクトースは果糖と言って単糖類の一種で…』と覚えてしまう人がいます。
この情報は脳にとっては大雑把なものではなく、細かい情報と認識されます。
ですので、次のように情報を少しずつ細かく落とし込んでいくのです。
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
| ステップ | 情報 |
| 1 | 炭水化物は〝糖質〟と〝食物繊維〟に分類される |
| 2 | 糖質は〝多糖類〟〝少糖類〟〝単糖類〟に分類される |
| 3 | 単糖類の中に、フルクトースがあり〝果糖〟と呼ばれる |
このように、まずステップ1で大きな全体像を捉えてから、ステップ2,3と徐々に細か情報にすることが重要です。
そうすることで、脳がストレスを受けずに、その情報を受容することが可能になります!
これは国家試験対策のどの分野における勉強でも同じで、いきなり細かい知識を入れようとしても脳に拒否されてしまい、上手く記憶できません。
では、どのような情報から把握すればよいのか?
それは『今学んでいる教科は何なのか?』から記憶するようにすると良いです!
先ほどの糖質のフルクトースの例でいうと
| ステップ | 情報 |
| 1 | 食べ物と健康という分野を勉強している |
| 2 | その中の〝糖質〟〝炭水化物〟について勉強している |
| 3 | 炭水化物は〝糖質〟と〝食物繊維〟に分類される |
| 4 | 糖質は〝多糖類〟〝少糖類〟〝単糖類〟に分類される |
| 6 | 単糖類の中に、フルクトースがあり〝果糖〟と呼ばれる |
このような感じの順番で、最初は大まかに、徐々に細かい情報を脳に入れていくと、すんなり理解することができるようになります!
特徴④ 脳は繰り返しにより記憶を作る

特徴②の『脳はそもそも忘れる器官である』でも少し解説しましたが、私たちの脳は繰り返しによってその記憶が定着していきます!
あなたは、次の項目について当たり前ですが、簡単に答えられると思います。
- 自分の名前
- 電話番号
- 住所
- 自分の家までの道順
たまに住所を思い出せないことがあるかもしれませんね・・・笑
これらは、全て長年の〝繰り返し〟によって強固に記憶されています!
生活の中で、何回も記憶を呼び起こしてアウトプットする中で、脳が『この情報は重要だ!』と判断し、インプットしているのです♪
また、特に意識をしていなくても、電車の窓を流れる風景って勝手に覚えてしまいますよね?
これも繰り返しによる効果です!
つまり、脳は時に意識をしていなくても、その情報に繰り返し触れることで、記憶として定着させる力があるということです!
ですので、国試の勉強でも繰り返せばOK!
そして、この繰り返しにはベストタイミングが存在しますので、別の記事で解説します♪
特徴⑤ 脳は欲した情報しか得られない

昔、クラスにこんな友達いませんでしたか?
九九は全く覚えられないのに、ポケモンや昆虫にやたら詳しい子!
他にも、好きな野球選手や好きなアイドルの名前なら無限に言える子もいるでしょう。
あなたがそうだったかもしれません!
このことからもわかるように、人間の脳は欲した情報しか得られないようになっています。
その子にとっては、九九は『必要ない情報』で、ポケモンや昆虫の名前は『必要な情報』だったに過ぎません。
あなたがこの記事にたどり着いたということは、栄養学が好き、もしくは興味があって大学や専門学校に入っているはずです!
ですので、自信を持って勉強しましょう!
特徴⑥ 脳は喜怒哀楽は忘れない
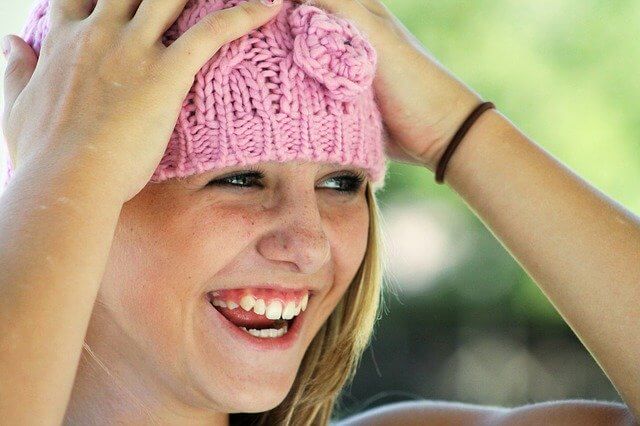
街を歩いていると、ほんの一瞬、昔好きだったあの彼(彼女)と同じ香りが・・・
(ド〜ルチェ ア〜ンド ガッバ〜ナ〜のその香水のせいだよぉ〜♪的な?笑)
こんな経験ありませんか?
そして、その香り共に、彼(彼女)と過ごした楽しく、寂しく、嬉しく、悲しかった日々の記憶が蘇ります。
そこでよく考えてみてください!
その、楽しかったこと、寂しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったことなど、これら全ての個々の思い出は、一度しか経験していないはず!
どういうことかというと、2年のお付き合いがあり、2回誕生日を祝ってもらったなら、きっと2回とも覚えていると思います。
3回大げんかをすれば、3回とも、その時のシーンを鮮明に思い出すことができるでしょう!
このように、どれもたった1回の経験にも関わらず、どうしてこんなにハッキリと何年もの間、記憶していられるのでしょうか?
なぜなら、脳は感情と結びついた情報は深く記憶に刻まれるようになっているからです。
いわゆる『心で記憶する』というやつです。
一方で大学の授業などは、先生が何度『ここ大事だよ!』と言っても覚えられません。笑
それは、心が動いていないからです。
つまり、感情をフルに使って勉強すると、たった一度の学習でも完璧に記憶することが可能です!
このように勉強することで、勉強時間が大幅に短縮することができます。
とにかく、勉強しながら笑える語呂を考えたり、なるべく感情に訴えかける工夫をすること♪
特徴⑦ 脳はストレスが天敵である

『あ〜勉強のしすぎで疲れたぁ〜』
『あ〜ストレス溜まるわぁ・・・』
こういう時は、思い切って勉強を休んだ方が、かえって効率的に勉強が進みます♪
- ストレスがたまる or 疲れる
- →勉強するけど集中できない
- →時間が無駄に過ぎていく
- →そんな自分が嫌になる
- →セルフイメージが下がる
- →ストレスがたまる or 疲れる
過度なストレスは、肉体的にも精神的にも良いものではありませんが、もちろん脳にもNG!
(適度なストレスは生きていく上で必要)
余計な不安を感じたり、感情がマイナスになることで、脳の作業効率も格段に落ちてしまいます。
できるだけストレスは上手く解消したり、避けたりして、脳にも良い環境を作りましょう!
特に今年はコロナの影響で、外出も人に会うのもNGと、ストレスをより一層溜め込みがち。
ぜひ自分のストレス解消法を確立し、試験勉強に対する免疫を獲得しておきましょう!
特徴⑧ 脳は寝ないと記憶が定着しない

〝記憶〟と〝睡眠〟は2つで1セットです。
これは、ほとんどの人が知っていると思います!
記憶には、〝短期記憶〟と〝長期記憶〟の2つに大きく分類することができます。
短期記憶の容量は少なく、これで試験に挑んでも、その壁の高さに跳ね返されてしまいます。
一方で、名前、電話番号、住所などと同じように、長期記憶による知識で試験に挑むことができれば、合格する確率は高くなります!
この長期記憶を形成する要因こそ、日々の質の良い睡眠になるのです!
しっかりと睡眠をとることによって、脳はその日の学習内容を記憶していきます。
最低でも1日6時間は寝ましょう!
つまり、管理栄養士の国家試験を合格したいなら、毎日勉強してちゃんと寝ろってことです!笑
まとめ
最後に、今回の記事の内容をまとめていきます!
- 繰り返し繰り返し情報に触れる
- 脳は忘れる器官であると受け入れる
- まずは物事を大雑把に捉える
- 勉強を好きになる
- 感情を爆発させて勉強する
- ストレスは上手に発散する
- 毎日できるだけ早く寝る
以上!